鼻水が止まらない!目が痒くて集中できない!なんとなくだるいかも・・・。
毎年この時期になると出てくる花粉症。
困りますよね。
今回は腸内環境が花粉症に及ぼす影響と対策、治療法についてお届けしますので参考にしてみてください。
それではいってみましょう!
花粉症とは?

そもそも花粉症とはどういったものでしょう?
政府が発表している内容では、「樹木や草花の花粉が原因となり、鼻水やくしゃみ、目のかゆみ、のどの痛みといった、さまざまなアレルギー症状を起こす病気。花粉症の原因はスギやヒノキなどだけでなく日本では、シラカンバやハンノキ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギなど、およそ60種類の花粉が花粉症を引き起こすと報告されている」と記載されています。
花粉症の諸症状は、原因となる花粉が飛散する時期に現れます。スギやヒノキの花粉の飛散は春、特に2月から4月がピークですが、夏に多いイネ科や秋に飛ぶブタクサ、ヨモギなどの植物もあります。花粉は雨上がりの翌日、晴れて気温が高く、風が強い日の昼前後と夕方に多く飛散します。毎年決まった時期に鼻水やくしゃみ、のどの痛みなどの症状が出る人は、その時期が何か特定の植物の花粉飛散時期と重なっていないか確認してみましょう。
花粉症の人ってどのくらいいるの?
2019年に実施された全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした鼻アレルギーの調査では、花粉症の人の割合はなんと42.5%!!!
特にスギ花粉症の人の割合は38.8%とのことで、日本人の約3人に1人がスギ花粉症と推定され、多くの日本人がスギ花粉症に悩まされていることがわかりました。
なんで花粉症になるの?
花粉症は花粉を吸ったからといってすぐに花粉症になるわけではありません。
体内に花粉が侵入してくると、体では免疫が働いてそれを異物と認識し、この異物(抗原)に対する抗体がつくられます。
数年から数十年かけて同じ種類の花粉が体に入ることで、抗体が生成され花粉症の発症に十分な量になります。
この状態を感作(かんさ)と言います。
感作後に再び同じ種類の花粉が体の中に入ってくると過剰な免疫反応が起こり、くしゃみや鼻水、涙などの症状がでてくるようになります。この状態が花粉症です。
このアレルギー反応には脂肪細胞と、IgE抗体というものがポイントとなってきます。
IgE抗体で捉えた花粉の抗原が脂肪細胞を活性化させることでヒスタミンという物質が分泌され、それにより種々のアレルギー症状を引き起こします。
花粉症を発症させないためには?
ではどうすれば花粉症になるのを防げるのでしょうか?
近年の研究で花粉症発症に腸内環境が関係していることがわかってきました。
腸内フローラの多様性が低下したり、腸内フローラの乱れ(ディスバイオシス)が起きたりすることが、この感作に重要な役割を果たしている可能性があるようです。
例えば、スギ花粉症の人では、腸内フローラの乱れとしてバクテロイデス目の腸内細菌が多いという特徴を示すことが報告されています。
特にバクテロイデス・フラジリスとバクテロイデス・インテスティナリスという菌が花粉シーズン前から花粉症患者で有意に多くなっており、試験前後で菌数が花粉症の自覚症状スコア及び花粉シーズン末期における血中スギ花粉特異的IgEレベルと有意な比例関係を示した事から、これらの菌種と花粉症発症との関連が示唆されたという論文も報告されています。
つまり免疫系が異常に反応して、IgE抗体が異常に作られ、これが脂肪細胞を刺激することで花粉症の症状が誘発されます。
これら2菌種は花粉シーズン終了時には菌数がさらに増加しており、アレルギー症状を重篤化させる悪循環が生じていると考えられます。
また、花粉症は複数種の植物の花粉が原因となる場合があり、すでに花粉症の人でも別の植物を原因とした花粉症を発症する可能性があります。別の花粉を原因とする花粉症を発症しないように、日常的に腸内環境を整えて予防することが大切と言えますね。
食べ物で気をつける事

では日常生活では何に気をつけたら良いのか。まずは食べ物に関して解説します。
いくつかの研究から、乳酸菌やビフィズス菌の特定の菌株が自然免疫系の活性化と免疫のバランス調整を行い、花粉症のアレルギー症状を改善することが示されています。
具体的には、スギ花粉症の人が以下の菌をプロバイオティクスとして摂取すると、症状がある程度改善したとの報告があります。
・ラクトバシラス・パラカゼイKW3110株(Lactobacillus paracasei KW3110)
・ラクトバシラス・アシドフィルスL-55株とL-92株(Lactobacillus acidophilus L-55/ L-92)
・ラクトバシラス・カゼイシロタ株(Lactobacillus casei Shirota)
・ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536株(Bifidobacterium longum BB536)
など
上記の菌株を含むヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリメントも販売されているため、花粉症にお悩みの方は商品のパッケージなどでチェックしてみてはいかがでしょう?
特にビフィドバクテリウム・ロンガムBB536株の摂取によりこれら先ほどの2菌種の増加が抑制され、アレルギー症状が出る悪循環が防止されることで花粉症症状の軽減に繋がっているのではないかといった論文も発表されています。
多くの方から質問いただいているヨーグルトの選び方に関してはまたの機会に解説したいと思います。
また、乳酸菌生成エキスを摂取することでスギ花粉症の改善が見られたという報告もあり、この件に関しても期待されています。
乳酸発酵でできている食品としてはヨーグルトの他に
・キムチ
・ぬか漬け
・ザワークラフト
などがあります。
ただし、特にキムチを購入するときは発酵しているかどうか確認してから購入しましょう。しっかり発酵させて作られたキムチは乳酸菌によって良い成分が作られますが、発酵せず調味料でキムチ味にしたものでは期待される良い成分が作られないため効果が全く異なります。
乳酸菌発酵しているキムチと、そうでないキムチ商品を見分けるには、以下の点をチェックすると良いと思います。
1. 成分表示:乳酸菌や発酵の記載があるか?保存料(ソルビン酸など)が使われていないか?保存料が入っているものは発酵していない可能性が高いです。
2. 製造過程:「熟成」「発酵」といった記載があるか?また、韓国産であるものは発酵されたものが多いのでその記載があるか?
3. 保存方法:冷蔵必須か?時間が経つと容器が膨らむか?容器が薄いフィルムで覆われただけの簡易的な商品は発酵されていない可能性が高いです。発酵によってガスが発生しても変形しない硬い容器に入っていますか?
4. 味と香り:開封してから徐々に乳酸発酵独特の酸味が増していくか?味が変わらないものは乳酸発酵していない可能性が高いです。
これらを意識することで本物の発酵キムチを選びやすくなります。発酵食品としての健康効果を得たい場合は、ぜひ乳酸菌が生きている本物のキムチを選びましょう。
日々の生活でできる花粉症対策
・外出するとき
マスクの着用:マスクの着用で通常のマスクでは約70%減少、花粉症用のマスクでは約84%の花粉を減少させる効果があるとされています。顔にフィットし息がしやすいもの、衛生面からは使い捨てのもの、性能的な面からは不織布のマスクがおすすめです。
メガネの着用:花粉症用のメガネも販売されていますが、通常のメガネを使用するだけでもメガネをしていないときより目に入る花粉量は減少します。コンタクトレンズを使用している人はコンタクトレンズによる刺激が花粉によるアレルギー性結膜炎を悪化させてしまうため、可能であればメガネに替えたほうがよいとされています。
花粉が付着しにくい服装:外出時はウールなどの花粉が付着しやすい衣類は避け、綿など花粉が付着しにくい衣類を選びましょう。また、頭と顔は花粉が付着しやすい部分ですが、帽子をかぶることで頭への花粉の付着量を減らすことができます。
・外から帰ったとき
家の中に花粉を持ち込まない:建物に入る前に衣類に付いた花粉を払い落としましょう。コートなどの衣服をはらうだけでかなりの花粉が落ちます。
うがいと洗顔:外出先から帰ったら必ずうがいを。のどに付着した花粉を除去する効果があります。また、顔を洗うことで顔に付着した花粉を洗い落とします。しかし、丁寧に洗顔をしないと目や鼻の周囲に付いた花粉が体内に侵入し、かえって症状が悪化することがあるので注意が必要です。
・家に居るとき
換気時は窓を小さく開け、時間を短く:花粉が飛んでいるときでも室内の換気が必要な場合があります。換気時は窓を全開にせず、10cm程度にし、レースのカーテンをすることで室内に入ってくる花粉を減らすことができます。流入した花粉は床やカーテンなどに多数残っているので掃除やカーテンの洗濯をしましょう。
こまめに掃除する:室内には衣類や髪の毛などに付着して花粉が持ち込まれたり、換気時に窓から花粉が入ったりしてたくさんの花粉が残っています。こまめに掃除機をかけ、室内の花粉を減らしましょう。
また、花粉の体内侵入を防ぐために花粉の飛散量が多い昼前後や夕方 は外出を避けるようにしましょう。
花粉症の治療方法は?
上記の対策をしても症状が出てしまうと辛いですよね。治療法はどういったものがあるのでしょうか。薬剤師の知識を活かしてお伝えします。
花粉症の治療は他の鼻や眼のアレルギーの治療と基本的には同じですが、急激に花粉にさらされるため、急性の強い症状への配慮も必要となります。
治療法を大きく分けると、症状を軽減する対症療法と根本的に治す根治療法の二つがあります。
対処療法としては内服薬による全身療法や点眼、点鼻薬などによる局所療法があります。
内服薬としてはルパタジン、デスロラタジン、ビラスチン、フェキソフェナジン、レボセチリジン、ロラタジン、オロパタジン、ベポタスチン、セチリジン、エバスチン、エピナスチンなどの抗アレルギー薬があります。また、エピナスチンやオロパタジンなどの点眼薬、そしてステロイドのフルオロメトロンなどの点眼薬、フルチカゾンなどの点鼻薬などが組み合わせられます。
くしゃみ、鼻汁が強い症状の場合は上記に記載した内服薬が多く使われますが、鼻閉が症状の主体である場合にはモンテルカストなどがより適応となります。どの症状も中等症以上になった場合には主として鼻噴霧用ステロイド薬が用いられます。より鼻づまりが強い場合にはナファゾリンなどの点鼻用血管収縮薬や時に内服のステロイド薬を使う場合があります。
抗アレルギー薬の中には眠気が強く出るものがあります。それと、血管収縮薬は使いすぎると血管が薬剤に反応しなくなり逆に拡張し続けるため鼻閉がひどくなる場合があり注意が必要です。市販薬の点鼻薬にも含まれていますので注意して使用しましょう。
また、症状の強い場合に処方されるステロイド点眼液は眼圧の上昇に注意が必要ですので、特に緑内障の症状がある方は処方してもらう時に医師、薬剤師に相談しましょう。
根治療法としては原因抗原(花粉など)の除去と回避、減感作療法(抗原特異的免疫療法)があります。
特に減感作療法は抗原特異的な免疫療法とも呼ばれ、花粉の抽出液を取り入れることで体を慣らしていく治療法です。特にシダキュアなどの舌下免疫療法があります。治療開始から数ヶ月で効果が出てきて、症状が完全に抑えられない場合でも症状を和らげ他の薬剤の使用量を減らすことが期待できます。シダキュアを5年ほど継続するとほぼ完治したと実感できる方が多いようです。ただし、重度の気管支喘息がある方は事前に相談しましょう。
いかがでしたでしょうか?
今回は花粉症についてお伝えしました。
次回もお楽しみに!


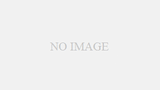
コメント