ニキビ(尋常性ざ瘡)は、美容だけでなく心理的にも大きな負担となる皮膚疾患です。デートや特別なイベントの前にニキビがあるとガッカリしますよね。
今回は薬剤師の視点からニキビと腸内環境や他の病気との関係を解説します。(次回は治療法や日々のケアで気をつけるポイントについてお伝えします!)
ニキビの原因は?

そもそもニキビはなぜできるのでしょう?
原因としては皮脂の過剰分泌や毛穴の詰り、アクネ菌や黄色ブドウ球菌の増殖、それに伴う炎症反応が挙げられます。思春期やホルモンバランスの変化により皮脂腺が活発になり、皮脂が過剰に分泌されることで皮脂や角質が毛穴に溜まり毛穴が閉塞。その毛穴内でアクネ菌が増殖し炎症を引き起こします。
放置すると炎症が悪化し、膿を持つ膿疱や膿瘍、さらには瘢痕(傷跡)を残す可能性があります。
腸内環境とニキビの関連性
腸内環境の健康状態は全身の健康状態に深く関係しています。最近の研究では、腸内環境の乱れがニキビを含む皮膚疾患の発生や悪化に関係するといった結果がわかってきました。腸内環境とニキビの関連性について、そのメカニズムを順を追って説明します。
腸内環境の乱れと炎症の全身的影響
腸内環境が乱れると腸のバリア機能が低下し腸の透過性が高まることがあります。この状態は「リーキーガット症候群」と呼ばれ、通常は腸内にとどまるべき細菌や未消化の食物、毒素が腸壁を通過して血液中に入り込みます。これにより免疫系がこれらを「異物」として認識し、全身で慢性的な炎症反応が引き起こされます。
ニキビは毛包や皮脂腺の炎症によって発生する疾患であり、炎症性サイトカインという物質が過剰に産生されることがその原因の一つです。腸内環境の乱れにより炎症性サイトカインの産生が促進されることで皮膚にも影響を及ぼし、ニキビの発生や悪化に繋がっています。
腸内細菌叢と免疫系の調整
腸内には100兆個の細菌が存在していると言われており、いわゆる「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」がバランスを取りながら共存しています。善玉菌は、短鎖脂肪酸(乳酸、酪酸、酢酸、プロピオン酸など)を生成し、腸粘膜の健康を保つほか、炎症を抑える作用を持っています。このバランスが取れている状態が健康的な腸内環境とされます。
しかし、いわゆる悪玉菌が優位になると腸内細菌叢が乱れ、炎症性物質(リポ多糖など)が増加し、免疫系が過剰に活性化されます。このような状態では、皮膚の免疫応答も過敏になり、ニキビを含む炎症性皮膚疾患が悪化する可能性があります。
腸と皮膚の相関関係(腸皮膚相関)
「腸皮膚相関」とは、腸内環境と皮膚の状態がそれぞれの健康に影響を及ぼすことです。この相関関係には、腸内細菌の代謝物や免疫系、神経系、ホルモン系などが関係しています。糖尿病や他ホルモン関連の疾患に関しては後ほど解説します。
短鎖脂肪酸
善玉菌が生成する短鎖脂肪酸は、腸のバリア機能を強化し結果的に全身の炎症を抑制します。これにより皮膚の炎症も軽減されます。一方で、腸内環境が悪化し短鎖脂肪酸の産生が減少すると、皮膚の炎症リスクが高まります。
腸内毒素の影響
悪玉菌が増殖すると腸内で生成されるリポ多糖などの毒素が血流を通じて全身に拡散します。これが皮膚に達するとニキビをはじめとする炎症性皮膚疾患を悪化します。
神経系やホルモンの影響
腸と脳は「腸脳相関」を介して密接に連携しています。ストレスや不安が腸内環境を悪化させこれが皮膚の状態にも反映されることがあります。例えば、ストレスにより腸内細菌叢が乱れると皮脂腺の分泌が増えたり炎症が促進されたりします。
高脂肪食や高糖質食が腸内環境とニキビに及ぼす影響
高脂肪食や高糖質食は悪玉菌の増殖を助長し腸内環境を悪化させる要因となります。特に高グリセミック指数(GI)の食品は血糖値を急上昇させ、それに伴いインスリンの急激な分泌を促進します。インスリンはIL1βやIGF-1の過剰な増加を引き起こし、これにより皮脂腺が活性化しニキビの悪化リスクが高まります。特に、果糖ブドウ糖液糖など精製された糖分が多く含まれる食品は注意が必要です。
疾患やホルモンとニキビの関連性
糖尿病などとの関連性
糖尿病などの代謝性疾患は、インスリン抵抗性や高血糖が皮脂腺の機能に影響を与えることで、ニキビを悪化させることがあります。高血糖の状態は炎症性サイトカインの分泌を促進し皮膚の炎症を助長します。また、糖質の多い食事はインターロイキン1β(IL1β)やインスリン様成長因子1(IGF-1)といった物質の分泌を増加させ、皮脂腺の活動を活性化させることでニキビの発症を誘導することが報告されています。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
PCOSは内分泌疾患で、アンドロゲン(男性ホルモン)が過剰に分泌されます。このアンドロゲンが皮脂腺を刺激し、皮脂の過剰分泌を引き起こします。その結果毛穴が詰まりやすくなり、アクネ菌が繁殖しやすい環境が整います。実際、PCOSがある方の約70~80%が顔面や体幹部にニキビを認めるとの報告があります。また、PCOSに伴う月経不順や肥満もホルモンバランスの乱れを助長し、ニキビの悪化要因となります。
月経周期とホルモン変動
月経周期に伴うエストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンの変動は皮脂腺の活動に影響を与えます。月経前のプロゲステロン増加は皮脂分泌を活性化させるため、ニキビの悪化が起こりやすいとされています。さらに、月経前症候群(PMS)や月経痛などのストレスも副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の分泌を促進し、皮膚の炎症を悪化させる可能性があります。生理前は気分もモヤモヤしたり気になりますよね。
また、心理的な要因もニキビの発症や悪化に深く関与しています。慢性的なストレスは、副腎皮質ホルモンの過剰分泌を引き起こし、皮脂腺を刺激します。ストレスは腸内フローラのバランスを崩し、腸皮膚相関を通じて皮膚の状態に悪影響を及ぼします。さらに、ニキビそのものが患者の精神的苦痛を増加させる「悪循環」を形成し、抑うつや不安症状を伴う場合も少なくありません。
ニキビかどうかのチェック方法

ニキビ(尋常性ざ瘡)は、一般の方でも自分である程度判断することが可能です。ただ、他の皮膚疾患との区別が難しい場合もあるため、自己判断が難しい場合や症状が悪化する場合には必ず皮膚科を受診してください。
・丘疹(赤い盛り上がり)があるか
毛穴が詰まり、皮脂が溜まって炎症を起こすと、赤い小さな隆起(丘疹)が現れます。これはニキビの炎症初期の特徴的な兆候です。
・膿疱(白い膿が溜まった部分)が見られるか
ニキビが進行すると、毛穴内部に膿が溜まり、白い膿疱が形成されることがあります。これも典型的なニキビの症状です。
・毛穴が黒ずんでいるか(黒ニキビ)
毛穴が詰まり、皮脂や角質が酸化すると、黒い点のように見えることがあります。これを「開放面皰(黒ニキビ)」と呼びます。
・白い盛り上がり(白ニキビ)があるか
毛穴の入り口が閉じて詰まっている場合、皮脂や角質が溜まり、白っぽい小さな盛り上がりとして現れることがあります。これを「閉鎖面皰(白ニキビ)」と呼びます。
・皮脂が多く分泌されているか
額、鼻、顎など皮脂腺が活発な部位にニキビができやすいです。特に皮脂が多い場合は、ニキビができるリスクが高くなります。
・ニキビの好発部位に症状があるか
顔(額、鼻、頬、顎)、背中、胸など、皮脂腺が多い部位に発生している場合、ニキビである可能性が高いです。
・思春期以降に症状が現れたか
思春期以降、ホルモンバランスの変化により皮脂分泌が増加し、ニキビができやすくなります。ただし、大人になってからもホルモンバランスや生活習慣により発生することがあります。
・かゆみがほとんどないか
ニキビは基本的にかゆみを伴わないことが多いです。かゆみが強い場合は、アレルギー性皮膚炎や他の疾患の可能性があります。
・症状が慢性的に続いているか
ニキビは通常、慢性的に繰り返し発生します。一度治ったと思っても、再発を繰り返す場合はニキビの可能性が高いです。
・他の疾患(湿疹や帯状疱疹など)と異なる特徴があるか
湿疹はかゆみが強く、発疹が広範囲に広がることが多いです。帯状疱疹は水疱が線状に分布するのが特徴です。これらと比較して、ニキビは毛穴を中心にした局所的な赤みや膿疱が特徴的です。
上記のポイントに当てはまる場合でも、他の疾患との鑑別が難しい場合があります。特に、症状が広範囲で重症化している場合、または長期間改善が見られない場合は皮膚科専門医の診察を受けることが必要です。自分で潰したり、触ったりすることは感染を広げるリスクがあるため避けましょう。
今回はニキビの原因や腸内環境との関連性、他の病気との関係についてお伝えしました。
次回はニキビの治療方法や日常で気をつけたいポイントについてなどをお届けしたいと思います。


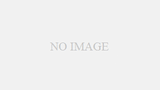
コメント